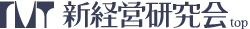- 2010-04-12 (月) 17:41
- 異業種・独自企業研究会
と き : 2010年03月10日
訪 問 先 : 本藍染 紺九 ⟨滋賀県・野洲⟩
講 師 : 本藍染 紺九四代目 森 義男氏
コーディネーター: 相馬和彦氏 (元帝人(株)取締役 研究部門長)
 「異業種・独自企業研究会」の2009年度後期第5回例会は、平成22年3月10日、滋賀県野洲市にある本藍染 紺九の四代目、国選定保存技術保持者の森義男氏の工房をお訪ねした。紺九では、藍の栽培からすくもづくり、藍建て、藍染めまで一貫して行い、また木灰による天然灰汁建てにこだわる数少ない紺屋である。化学染料では不可能といわれる深みのある藍を出す工程を見学し、自然と共生しながら伝統の技を維持しかつ磨いてきた精神を知ることで、これからの日本のものづくりに多大の示唆が得られることを期待して訪問した。最初に森義男氏とご長男の芳範氏のお二人に、敷地内の藍染め各工程のご案内をいただいた。
「異業種・独自企業研究会」の2009年度後期第5回例会は、平成22年3月10日、滋賀県野洲市にある本藍染 紺九の四代目、国選定保存技術保持者の森義男氏の工房をお訪ねした。紺九では、藍の栽培からすくもづくり、藍建て、藍染めまで一貫して行い、また木灰による天然灰汁建てにこだわる数少ない紺屋である。化学染料では不可能といわれる深みのある藍を出す工程を見学し、自然と共生しながら伝統の技を維持しかつ磨いてきた精神を知ることで、これからの日本のものづくりに多大の示唆が得られることを期待して訪問した。最初に森義男氏とご長男の芳範氏のお二人に、敷地内の藍染め各工程のご案内をいただいた。
1.試験圃場
 藍の栽培を試験する小規模の圃場が庭にある。藍はタデ科で、草丈は60㎝程度に達する。葉には苦みがあり、防腐・除虫作用があり、栽培は容易である。
藍の栽培を試験する小規模の圃場が庭にある。藍はタデ科で、草丈は60㎝程度に達する。葉には苦みがあり、防腐・除虫作用があり、栽培は容易である。
圃場の脇に石組みの洗い場跡がある。昔はここで藍染めを洗うことが出来たが、今では排水制限のため使用されていない。藍の圃場は外に所有しており、一部は契約している藍栽培農家からも購入している。藍の品種改良はやっておらず、在来種を継代使用している。藍の原産地は中国
2.発酵室-すくも作り
藍の発酵に使用されているのは築140年の古い建屋で、発酵菌が内部に住み着いているのは酒や味噌などの醸造業と一緒である。もしこの建屋を建て替えたり、壊したりすると、発酵菌が変わってしまうという懸念があるので、大切に使用している。
発酵には2ヶ月半ほど掛かり、毎日温度調節を行う。発酵の進み具合は、発生するガスの臭いで判断するのだという。終了段階になると、硫黄化合物のような臭いになる。湿気防止のためもみ殻を敷き詰め、その上にムシロを敷いて発酵させる。
発酵には地下水を使用し、寒期の発酵がベストである。藍の葉は藍染めに、茎は胃腸薬に使用されるので無駄がない。発酵後の藍(すくも)は、俵詰めにして貯蔵する。すくもの品質は、産地と生産者によって異なっている。
3.乾燥
藍染めした糸の乾燥は天日で行う。たまたま色調の異なる3色の染糸が干してあったが、商品としては8色の染めが可能。染糸の80%は修復用の材料として供給しているが、素材としては絹が多く、綿、麻もある。淡色から濃色への変化は、何回も染めることによって濃色を出した方が安定化する。甕によって色の違いがあるので、薄色から始めて段々に濃色に漬けて行く。
4.染め工場-「丁場」
①灰汁取り。
 ツバキ、葦、藍の茎から取った灰を樽に詰め、地下水に漬けて灰汁を取る。紺九では、今でもすくもと灰汁のみを使って藍染めをしている。昔は灰汁取りに葦の灰を使っていたが、今は出来なくなった。
ツバキ、葦、藍の茎から取った灰を樽に詰め、地下水に漬けて灰汁を取る。紺九では、今でもすくもと灰汁のみを使って藍染めをしている。昔は灰汁取りに葦の灰を使っていたが、今は出来なくなった。
②脱脂 絹糸には油があるので、湯で炊いて脱脂してから染色する。
③丁場
藍染め用の甕は全部で33個あり、甕は地中に埋め込まれている。4個の甕が近接して置かれているグループが6組あり、中央の穴には炭を置いて加熱し、温度調整が出来るようになっている。
甕は毎日攪拌し、発酵が活発になるようにすると、甕の中心に藍の花が中心に出来る。藍の花は顔料が主成分であり、修復用に供給している。陶磁器の釉薬に欲しいという依頼もある。床は漆喰でつくられている。
 ④藍染めの実演
④藍染めの実演
森義男氏が自ら藍染めの実演をされた。絹糸の束を甕に漬け、一部を引き上げて空気に晒し、また漬ける作業を繰り返して均一に漬かるようにする。十分に漬かったと判断すると、絹糸の束を引き上げ、上部の棒を捻って水分を絞り出し、
絹糸を空気に晒と、焦げ茶色の糸が見る見る鮮やかなエメラルドグリーンに変化し、一瞬の内に藍色に変わる。これは、藍の酸化による発色であるそうだが、一瞬の見事な色の変化に目を奪われた。その後、絹糸だけでなく、和紙の染色も実演いただいた。
⑤藍染めの多色化
藍だけでも淡色から濃色まで、色の変化が可能であるが、藍に天然の色素を加えることにより、更なる多色化が可能となった。紺九で作られる8色の色を出すために、藍にカリヤス、キハダを加えて黄~緑色系統の色を、セブシを加えて黄茶~緑色系統の色を出している。
⑥洗い
「染め物は水で染める」と言われるほど、水の品質は染めの品質に多大な影響を与える。紺九では山から滲みだしてくる地下水を使用しているが、水道水を使用すると、色が濁ってしまうという。
⑦重ね染め
色を重ねて染める場合、染め→洗い→乾燥・定着(三日間)でまず一色を染め、別の色に対してこれと同じ工程を繰り返す。この時、空気との接触が均一になるよう、手で動かすことが重要である。
藍染め全行程の見学後は広間に集まり、森氏が製作して桂離宮修復時に使用した藍と白の市松模様の障子および藍色襖の実物を拝見した。襖のサイズに対し、染めた和紙が小さいため、多数の和紙を貼り合わせ襖サイズとしている。貼り合わせに使用した和紙の色は一枚毎に微妙に異なるということだが、大きな襖の色は全く均一に見え、それを可能にした職人の技に感嘆した。桂離宮の市松模様の障子や襖は調度との調和が見事なことで知られているが、現地では建屋内に上がることは禁止され、庭先からしか鑑賞出来ない。その市松模様の障子や襖と同じものを間近に見学し、その深みのある見事な藍色に感動した。
最後に森義男氏とご長男の芳範氏のお二人に出席いただき、質疑応答の時間を持った。伝統技術の技を身近に拝見した後なので、活発な質疑となったが、要点のみ以下に纏めた。
1.藍染め技術やノウハウは記録として残っているのか? 染めの仕様はあるのか?
→最初は記録を見たが、後は体で覚えた。注文主の色見本を見せられても、同じものは出来ないとはっきり言う。その都度出来上がりの色は異なるので、結果の色は任せて貰うことにしている。
2.法隆寺の宮大工 西岡常一さんは「不揃いの木を使って、真っ直ぐに見えるようにするのが宮大工の仕事だ」と言っていた。均一な色のものが良いのか?
→自然は均一ではない。染めた色は一品一品全部異なる。それを同じに見せる技がある。桂離宮の襖でも、貼り合わせた和紙一枚一枚の色は全部異なるが、それを使って貼り合わせた襖の色を均一に見せるのが職人の技だ。職人の仕事とは、「命、後世に残る、献身」の三つである。これがなくなれば日本は負ける。
3.「染め物は水で染める」という話だったが、これからの作業環境の変化にはどう対応していくのか?
→努力しかない。今までは染め物に適した水源があった。これからは問題化していく可能性がある。その場合には、現在の場所を変えても、染色を続けていくつもりである。また生糸の産地も多様化していく。特に東南アジア産が増えており、ブラジル産も出て来た。特性の違う生糸への対応も必要だ。
4.藍染めの後継者は?
→長男が30代までは外に出ていたので、後継者がない場合はやむを得ずと思っていた。戻ってきて満足の行くようになったのは最近。当分は下働きで修行させるつもり。
今回の訪問で一番印象的だったのは、森義男氏が自ら藍染めの実演をされ、絹糸の束を甕から引き出して水を絞り出した時、染めが焦げ茶色から目の覚めるような明緑色に変化し、一瞬の間にそれが藍色に変わった瞬間であろう。自然の神秘、奥深さを見る思いがした。藍色そのものも素晴らしい色であったが、あのエメラルドグリーンは一瞬の間しか出現しないがために、一層心に残ったのかも知れない。
見学から広間に戻った際、工房で染めた糸を使った、心が引き込まれるような藍色の和服生地や奥様手作りのマフラー、敷物、小物入れなどを手に取り、購入した参加者が多かったことからも、如何に強い印象を受けたかを伺うことが出来た。並べられた製品の藍の色も淡色から濃色までさまざまな色合いで、一つとして同じものがなく、自然の色の持つ奥深さを感じることが出来た。
 紺九は江戸時代から続く伝統技術を守り、最高品質の藍染めを行っているので、品質やそれを作り出す技については、宮大工、刀鍛冶、和紙、漆などの職人の考え方と共通するものがある。自然の資材を用い、自然の作りだす環境に従って、均一・画一的な品質のものを作り出すのではなく、例え不均一であってもそれを均一に見せる技を有し、結果的には高品質かつ長寿命な製品に仕上げていく技は、長年に渡って日本国土の自然に従って作り上げられたものである。
紺九は江戸時代から続く伝統技術を守り、最高品質の藍染めを行っているので、品質やそれを作り出す技については、宮大工、刀鍛冶、和紙、漆などの職人の考え方と共通するものがある。自然の資材を用い、自然の作りだす環境に従って、均一・画一的な品質のものを作り出すのではなく、例え不均一であってもそれを均一に見せる技を有し、結果的には高品質かつ長寿命な製品に仕上げていく技は、長年に渡って日本国土の自然に従って作り上げられたものである。
このようにしてつくられた製品には、つくった職人の心と命が宿り、それが後世に残る力になっている。グローバル製品と称される近代工業製品は、安価で一定の品質を保っているが、その中のどれくらいの製品につくり手の心が宿り、後世に残っていくのであろうか。工業製品であっても、かつてはつくる人の心が籠もり、後世に残る製品をつくり上げることが可能ではなかったのか。グローバル化の価格競争の中で、いつしかわれわれはそれを忘れてしまったのではないだろうか。それを再び思い出した時に、日本のものづくりの再生が可能になるのではないだろうか。そんな事を考える良い機会を与えられた訪問となり、少し豊かな心を抱いて紺九を辞去することが出来た。
(文責 相馬和彦)
- Newer: 時代の変革期、日本大転換への道筋を考える/出井伸之氏
- Older: 未曾有の企業環境を生きる!シャープの経営の軸、未来成長戦略