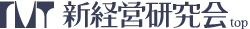Home > アーカイブ > 2008-10
2008-10
三洋化成のネットワークR&D戦略
- 2008-10-24 (金)
- 異業種・独自企業研究会
と き : 2008年9月24日
訪 問 先 : 三洋化成工業(株)桂研究所
講 師 : 代表取締役 執行役員副社長 増田房義 氏
コーディネーター: 相馬和彦氏 (元帝人(株)取締役 研究部門長)
2008年度後期の「異業種・独自企業研究会」第1回は、9月24日に三洋化成の桂研究所を訪問した。三洋化成は大量生産の汎用品ではなく、少量多品種の特殊化学品を製造する国内では数少ないメーカーである。過去多くのシーズを生み出してきた研究所を訪れることで、研究開発の源泉について大きな示唆が得られるのではないかという期待を持って訪問した。桂研究所は市内の本社敷地内にあった研究所が手狭になったため移設を決定し、本年6月に完成したばかりの新研究所であり、見学の最中も未だ一部では完全に移転が完了しておらず、ペンキの香りが残っているピカピカの状態であった。ここは京都駅から西の丘陵に位置し、吉田山から移転した京都大学桂キャンパスが隣接しているため、産学協同研究がやり易い利点がある。周囲は竹やぶに囲まれ、京都盆地を見下ろす好位置にあって、研究環境として優れていることが理解出来た。
最初に代表取締役執行役員副社長で研究・技術開発機能担当の増田房義氏からご挨拶があり、次いで桂研究所長兼開発研究本部 エネルギーデバイス材料研究部部長の河原裕氏より、「会社及び桂研究所概要」について説明がなされた。
三洋化成の研究開発費は売上の5%を投入し、5年間の新製品比率を40%に目標設定している。界面活性剤が会社のスタートであるが、研究所の壁に特許数の多い研究者名がリストアップされており、毎年Innovator of the Yearを表彰するなど技術開発を重視していることが伺えた。グローバル化に対しては、チャレンジ10の目標設定で挑戦している。
桂研究所の敷地は、桂イノベーションパーク内にあり、京都大学桂キャンパスが隣接している。ネットワーク型R&Dを目指し、大学、公立研究所、企業群との協力関係を重視している。京都大学では桂インテックセンターなどを活用している。
研究所の床面積は現在6,538㎡あり、収容可能人員は100名であるが(実際の在籍は80名、その外本社研究所に若干名)、将来は9,000㎡、200人収容まで拡張可能である。研究分野は電材、バイオ、環境に設定している。
次いで研究所内部を見学した。まず屋上に上がったが、遠くに比叡山、大文字焼きが見え、その手前は京都の町並み、近くは緑の竹やぶが一望されるため、好天にも恵まれて大変爽快な気分となった。最初はプロセス開発室を見学したが、射出成型機、加熱プレス機、反応器、フィルムの二軸延伸機などがあり、試作も行うとのことであった。実験室は実験台と机が隣接していて、研究員間の密接な情報交流が図られていた。研究開始から市販までに要する時間を尋ねたところ、早いもので半年、通常は1~2年と通常の化学品にしては大変早く、意思決定が極めて迅速に行われている企業風土が感じられた。
ショールームには、様々な分野の製品が陳列されており、製品数は3,000に達するとのことであり、少量多品種の実態が良く分かった。
次いで京都大学桂キャンパス内にある京都・先端ナノテク総合支援ネットワークを見学した。まずX線誘起光電子分光によるナノ構造表面評価装置およびナノファブリケーション装置を見学した。後者は物理的および化学的方法により、新しい機能のデバイス開発を目標にしている。いずれも企業が申し込めば、利用可能となっている。次にシステムシミュレーションラボを見学したが、建設会社との共同研究で、橋梁の耐震実験が行われていた。また風によって起こる波の状態を解析する装置で、稼動状況も見学出来た。この実験室も企業が申請すれば、5年間は継続利用が可能とのことであり、企業との共同研究や企業への設備開放が実施されていた。
見学から戻った後、本日の本題である講演「三洋化成のネットワーク型R&D戦略」を、増田房義副社長から伺った。
三洋化成は1949年に京都の町工場から出発した。当時三井物産と東洋レーヨンの出資を受け、社名を三洋化成と名づけた。遅れてきた会社なのでユニークな経営を目指し、創業当初から技術重視を経営方針とした。
「ニーシーズ指向」は1970年、「人中心の経営」は1990年頃から始め、手の届く施策を常にリニューアルすることを目指した。2008年3月期の売上は1,352億円、経常利益は58億円であるが、2004年からは原材料アップの影響を受けている。分野別では、ウレタン関連製品が25%、親水性高分子薬剤が23%、親油系高分子薬剤が21%、界面活性剤が18%、特殊化学品が12%、その他1%の割合である。また地域別売上では、国内が68%、海外が32%であるが、海外は輸出を含むため、海外の生産量自体はもっと低い。
経営方針として特徴的なのは、第一は人中心の経営である。具体的には、社員は明示された主責任と明示されない副責任を持つことである。第二はマトリックス運営で、営業と研究、ライン研究とコーポレート研究がマトリックスで運営され、常に両者をバランスさせている。毎年研究者の5%を外に出すことで、人的な交流を促進していることも、これらの方針が具体的に運営可能な理由になっている。
研究開発は以下のような方針に基づいて進めている。
①ニーシーズ指向で、独創的かつ高性能な製品を開発する。この方針の結果、製品総数として3,000個を上市している。ニーシーズ指向とは三洋化成の造語で、ニーズに対応して開発した技術に別の技術を複合させ、これをシーズとして新しいニーズに対応する製品を開発し、これを連鎖反応的に継続実施するというものである。ニーズ指向、シーズ指向の一方だけを追及するのではなく、両者を組み合わせて更に上のレベルを目指そうとしている。
②過去5年間の新製品・改良製品の比率を40%に維持する。これは常に新しい製品、改良製品を開発出来なければ達成困難な目標で、世界的にもこれと類似の目標を持っているのは3M位である。
③一人一人がチャレンジ出来るように、フラットな組織運営を行っている。組織としては、本部長-部長―RU(Research Unit)長とフラットで、RU当たりの平均人員は5~6名である。全体で430人在籍者がいるなかで、RU長は現在64人いる。
④「ビジネスクリエイト」というパーソナルチャレンジ制度があり、チャレンジは51件あったが、そのうちの17件が成功した。成功した人達は、その後RU長や研究室長へ昇格という評価を得ている。
組織は機能部制を取っており、これが成功確立のアップに貢献している。人の育成はOJTが基本で、近未来、未来、遠未来道場などいろいろな育成の場が社内に存在している。
過去の売上増加は、界面活性剤 → ウレタン関連製品 → 親油性高分子薬剤 → 親水性高分子薬剤 → 特殊化学品と発展したことによるが、それではこの次に何をやったら成長を継続出来るかが現在の課題となっている。ニーシーズ指向の行き詰まりかも知れない。77~80年は、新改良品の売上が138億で、売上比率が40.8%を占めていた。この時のR&Dには220人投入し、一人当たりの新改良品売上は63百万円であった。99~01年は、新改良品売上が270億円、売上比率は37%、R&Dには360人を投入したが、一人当たりの新改良品売上は75百万円に止まり、期待したような進歩が見られなかった。このまま同じやり方を継続して、果たして成長が維持されるのかという疑問が出て来た。
成長が遅くなった背景には、いくつかの理由が考えられる。
①ニーズが豊富だった時代に比べ、ニーズそのものが減少してきた。
②新しいニーズを捕まえるためにも、飛びぬけたシーズが必要となる一方で、化学業界自体の競争も激化して来た。
③企業内部の決定が上に上がる傾向があり、そのため決定の動きが遅くなって来た。
最近で成功した例を見ると、共通した特徴が見られる。
①ユーザーとの共研の中から具体化した。
②ユーザーの化学知識が豊富となってきたため、独創的なアイデアを提供した。
③決定権が上に行っているので、下での合意だけでは不十分となり、トップ同士を巻き込んで企業戦略と整合した商品を開発した。
そのため、今後は、以下のような方策を行い、ネットワーク型R&Dで対応しようと考えている。
①組織ぐるみの取り組みを行う。
②大学を入れた産学協力を推進する。桂インテックセンターに見られるように、大学も産学協力には熱心。
③日本の「和」を世界に発信する。
これがこれからのネットワーク型R&Dと考えている。
締めくくりに事業研究本部 研究業務本部 本部長の前田浩平氏より、「三洋化成におけるR&D事例研究」と題して、具体的な研究成果について講演があった。一部を以下に要約した。
①高吸水性樹脂(SAP)
殆ど紙おむつに使用されているSAPは、現在世界で170万tの生産規模に達しているが、三洋化成が世界に先駆けて開発したものである。76年にラボで合成したものを78年に商業生産した。83年から花王やユニチャームに採用され、市場が拡大した。94年からは原料のアクリル酸を製造する三菱化学とJ/Vを組み、グローバル化に成功した。
②永久帯電防止剤「ペレスタット」
ポリオレフィン製品の帯電防止剤で、PPに剤を練りこんだもの。
③インパネ用ウレタンビーズ
粒子径が良く揃ったウレタンビーズで、自動車用インパネとしてトヨタに採用された。研究から10年掛かったが、最近伸びている。両社の技術トップの合意が得られたため、開発へ迅速に進められた。
④ポリエステルビーズ
トナー用であるが、画像が鮮明の上、省エネ効果もある。これも技術トップ間の合意が得られてから、密接な関係が構築出来た。③、④の実例は、トップ間の合意で戦略的に進めることの重要性を示唆している。
内容が具体的かつ豊富で、R&D戦略の本質に迫る内容であったため、講演後の質疑応答が活発に行われたので、要旨のみ簡潔に纏めた。
①研究から事業化までの期間が、化学企業の一般常識からは極めて早いことについて。
事業化の際にあまり細かい事業性の議論はせず、むしろ市場の5%を取れるかどうかという点を重視して決断する。
②3000余の製品群を有し、かつ5年間の新改良品比率が40%を目標としているが、それぞれの製品の継続販売/中止決定をどのように行っているか。
三洋化成では個々の製品毎に事業性データがあり、それを研究と営業が共有しているため、継続/中止の合意が得られやすい。また3年間赤字を継続した場合には、原則その製品は中止するというルールもある。
③社員の育成方法は。
特に教育体系は持っておらず、OJTが基本である。
今回は、ユニークな多数の製品群が産み出されている三洋化成の研究所現場を訪問し、研究開発を指導している幹部役員の講演をお聞きすることが出来たが、その根本には研究者および社員を生かし、大切にする「人中心の経営」があることが理解出来た。どんなに良い制度を作っても、魅力的な給与体系を持っても、最後は技術を支える研究者のやる気を起す経営、すなわち「人中心の経営」に勝るものがないことを改めて痛感した一日となった。この考えさえあれば、経営環境がどのように変わっても、競業状況に変化があっても、常にその時に環境下で最適な経営が可能となり、企業は継続的に発展するであろう。また、新製品を次々に生み出す技術方策として、ニーシーズ法を実行している。筆者は企業の研究開発を担当していた頃から、新製品を継続的に産み出す方策として、①既存製品を支えるコア技術を確立する、②それだけでは新製品を産み出すのに限界があるので、新しいコア技術を自社で創り出す、③既存製品のコア技術と新しいコア技術を組み合わせて、新製品を産み出す、④このコア技術が既存製品のコア技術に追加される、⑤以上②~④を繰り返すことによって新製品を継続的に産み出すことを提唱して来た。筆者の提唱して来た方策と、三洋化成のニーシーズ法とは極めて近い考え方であり、それが成功してきたことに勇気付けられた。
(文責 相馬和彦)
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
Home > アーカイブ > 2008-10