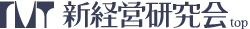Home > アーカイブ > 2007-10
2007-10
世界初、体内埋設型超小型補助人工心臓実現への夢と苦闘
- 2007-10-30 (火)
- 異業種・独自企業研究会
と き:2007年10月17日(水)
訪 問 先:(株)サンメディカル技術研究所 本社工場
(株)ミスズ工業
講 師:代表取締役会長 山崎壮一 氏
代表取締役社長 山崎俊一 氏
東京女子医科大学講師 山崎健二氏
コーディネーター: 相馬和彦氏(元帝人(株)取締役 研究部門長)
 平成19年度後半の第三回は、長野県諏訪市にあるサンメディカル技術研究所を訪問した。諏訪市は精密機械部品の集積都市として有名であるが、同研究所も兄弟会社の精密部品製造会社であるミスズ工業の敷地に隣接しており、経営的・技術的にも密接な関係にある。今回のサンメディカル技術研究所は、異業種・独自企業研究会で過去訪問してきたものづくり企業の中でも、埋め込み型補助人工心臓という特異な製品を製造している。精密機械ではあるが、生命維持のために必要不可欠であり、かつ一瞬の誤作動も許容出来ない心臓補助機器であるため、製品のコンセプトを初め、誤作動や不良品の排除、更には認可に至るまでの安全性確認、保険申請など、実用化に至るまでには様々な課題を克服せざるを得ない。
平成19年度後半の第三回は、長野県諏訪市にあるサンメディカル技術研究所を訪問した。諏訪市は精密機械部品の集積都市として有名であるが、同研究所も兄弟会社の精密部品製造会社であるミスズ工業の敷地に隣接しており、経営的・技術的にも密接な関係にある。今回のサンメディカル技術研究所は、異業種・独自企業研究会で過去訪問してきたものづくり企業の中でも、埋め込み型補助人工心臓という特異な製品を製造している。精密機械ではあるが、生命維持のために必要不可欠であり、かつ一瞬の誤作動も許容出来ない心臓補助機器であるため、製品のコンセプトを初め、誤作動や不良品の排除、更には認可に至るまでの安全性確認、保険申請など、実用化に至るまでには様々な課題を克服せざるを得ない。
補助人工心臓の開発の中心となったのは、東京女子医大心臓血管外科の准教授である山崎健二先生であるが、ご家族全員が一丸となってこのプロジェクトを推進している。サンメディカル技術研究所は山崎俊一社長、ミスズ工業は山崎泰三社長といずれもご兄弟が就任し、グループ企業全体をご尊父の山崎荘一会長が纏めている。聞くところによると、本プロジェクトの当初の開発資金は、会長の決断により家族保有株の売却で得た資金を当てたとのことで、家族全員の支援があってこそ今日の成功が可能であったことが分かる。
当日はまずサンメディカル技術研究所山崎俊一社長のご挨拶があり、ミスズ工業の紹介ビデオおよび「特ダネ」で放映された人工心臓に関するテレビ番組を見た後、グループに分かれて工場見学に移った。
ミスズ工業では金型制作、打ち抜き、メッキ、場合によってはその後の組み立てまで自社で行っている。元々はセイコーの部品供給から出発しているので、大きなものはやっておらず、小さな部品製造を得意としていて、自分で最後まで作り上げることを方針としている。従業員はミスズ工業全体で正社員が約500人、それに臨時社員がプラスされる。工場は国内に三ヶ所、中国に一ヶ所あり、諏訪工場には約300人が働いている。製品群を見せて貰ったが、時計部品から出発したと言うとおり、歯車などの部品も肉眼では細部が良く分からないほど細かい出来であった。工場では一年に二回、自分の好きなものを作って全員で評価する催しが行われているとのことで、ものづくりの原点を大切にしている社風が伺われた。
サンメディカル技術研究所では、研究開始以来試作した人工心臓が保存されており、技術の進歩がプロペラの形状変化やポンプ・バッテリーの小型化で具体的に理解出来るようになっている。人工心臓はいったん埋め込んだ後は永久使用を目的としているので、部品の寿命には気をつけている。故障を排除するため、製品コンセプトとしてメカニカルで作動するように工夫し、センサーや電気的な作動は避けていて、軸受けは50年、シール部分は25年の耐久試験に耐えるように作られている。血栓防止はMPCの内面コートで対応しているが、MPCが剥がれても血栓は起きにくいようである。羊を使用したテストでは、埋め込み後二年半で人工心臓を取り出して検査したところ、血栓はまったく形成されていなかったとのことである。部品は総て無垢のチタンから削り出したものを使い、製造のクリーン度も10,000から初めて1,000へ上げ、最後の工程では100にしている。一ヶ月に1個しか製造出来ず、製造コストも1個当たり1,300~1,500万円程度と高価であるため、保険申請では1,400万円で申請中である。現在保険がついている米国製は1,310万円なので、性能から言ってもこの位は合理的であろうと考えている。
講演会場へ戻ってから、東京女子医大心臓血管外科准教授山崎健二先生による体内埋め込み型補助人工心臓についての講演をお聞きしたが、医師としての使命感だけでなく、ものづくりのエンジニアとしての視点も極めて高く、ものづくりの本質でも教えられることが多い内容であり感銘を受けた。
補助型人工心臓は、拡張型心筋症という強心剤も効かなくなった末期の重症心不全の患者が対象となる。拡張型心筋症と診断されると、生存率は6ヶ月で26%、12ヶ月で6%と極めて低い。そのため、人工心臓に頼るか、心臓移植を受けるかしか選択肢がないが、後者は移植用心臓の供給数に限りがあり、移植後も拒絶反応が問題となる。人工心臓は米国でリンドバークが最初に提案し、1935年にプロトタイプが試作され、その後様々な形のものが提案されている。
重症心不全の患者数は、米国で5万~10万人、日本では2,000~3,000人と推定されている。補助人工心臓としては、HeartMateやNovaCoreがあり、薬物治療対比で生存率はアップするが、感染症、装置故障、脳血管障害などの合併症が課題となっている。そのため次世代の人工心臓が提案されており、軸流ポンプタイプではDeBakey、HeartMateなど、遠心ポンプタイプではEverheart(山崎先生)などがある。日本企業としてはサンメディカル技術研究所とテルモが開発しており、サンメディカル技術研究所は国内中心で、テルモは米国・欧州で治験を進めている。
サンメディカル技術研究所は、1991年に山崎先生の考案した補助型人工心臓を実用化するために設立され、2005年度より臨床試験を開始した。血液を送るポンプは2,000rpmを中心とし、患者毎に微調整した固定回転数に設定する。心臓の血液循環量は患者の運動量によって変動するが、心臓には拍動によって内部に圧力差が生じるため、ポンプの回転数が一定であっても、その圧力差の変動に応じてポンプの循環量が変動する。そのため、ポンプは固定回転数であっても、結果的に患者の心拍数に追随した血液量の調節が出来る仕組みになっている。ポンプは毎分14リットル以上送れるので十分な能力を有している。
人工心臓の内壁と血液の接触による血液凝固を防止するため、内壁には東大の石原先生の研究成果であるMPC(リン脂質)をコーティングしている。この装置を装着したヤギで823日間の稼動を確認しており、特に血栓の問題は認められていない。
治験プロトコールは、日米共通のものを末期の重症心不全患者で実施中であり、三分の二まで終了している。抗凝固剤としてアスピリン、ワーファリンの投与を併用している。医療費としては、入院中は毎月200万円掛かるが、退院後の自宅療養では毎月2~3万円で済む。治験は第1相が3名、第2相が11名で進めており、脳出血の合併症で亡くなった2名を除き、生存率は6ヶ月で91%、12ヶ月で78%、2年で78%と、強心剤投与(生存率は6ヶ月で26%、12ヶ月で6%)と比較し飛躍的に向上している(Kaplan-Meier法での推算による)。
2007年6月には医療ニーズの高い医療装置の早期導入対象に選ばれ、7月6日にオーファンデバイスの指定を受けたので、最初の関門は突破した今回の訪問で印象に残ったことを三項目に纏めた。①ニーズは高いが極めて事業リスクの高い目標への挑戦。大企業ではこういうリスクの高い事業を手掛けることは極めて難しい。それに挑戦するのは、これこそまさに「夢」と「志」がなければ不可能である。必ずしも当初は潤沢な資金に恵まれていなかったにも拘わらず、手持ちの株を手放してまで開発資金を捻出したことは、それを雄弁に物語っている。②技術課題の克服。埋め込み型の医療器具では、血栓形成および装置の故障が大きな障害となっている。特に人工心臓のように故障があってはならないような器具は、技術的障害も極めて高い。それを長い時間を掛け、一つ一つ解決していった努力には敬服した。血栓はMPC塗布とシール部の水循環により解決し、故障除去には徹底的なシンプル化で対処したとのことであるが、ものづくりに携わる我々にとっても、設計コンセプトそのものの段階から学ぶことが多い。 ③このプロジェクトは会長を中心とした3人のご兄弟のチームワークなしには不可能であった。毛利元就の三本の矢のエピソードにもあるように、協力こそ強力な力となる。父親の存在感そのものが弱くなった現在では、非常に珍しい例ではないだろうか。講演中再三示されたように、健二先生はエンジニアとしての見識も極めて高く、心臓外科の専門医である先生がエンジニアとして一流のセンスをどうやって取得したものかに興味を惹かれた。最後のパーティーで伺ったところ、先生はピッツパーグ大学の大学院に留学中、自分が知りたいと思った専門外の学問を積極的に学ぶことに心がけ、医学以外についても習得することが出来た。その後になって人工心臓の開発を始めてからも、自分の知らないこと、必要なことはそれぞれの専門家から積極的に学ぶことを心がけた結果、様々な課題を解決することが出来たとのことであった。「壁は自分で作るものだが、それを除くことは出来ますよ」と穏やかに話された言葉は、技術者としての我々に対するまさに頂門の一針であった。(文責 相馬和彦)
③このプロジェクトは会長を中心とした3人のご兄弟のチームワークなしには不可能であった。毛利元就の三本の矢のエピソードにもあるように、協力こそ強力な力となる。父親の存在感そのものが弱くなった現在では、非常に珍しい例ではないだろうか。講演中再三示されたように、健二先生はエンジニアとしての見識も極めて高く、心臓外科の専門医である先生がエンジニアとして一流のセンスをどうやって取得したものかに興味を惹かれた。最後のパーティーで伺ったところ、先生はピッツパーグ大学の大学院に留学中、自分が知りたいと思った専門外の学問を積極的に学ぶことに心がけ、医学以外についても習得することが出来た。その後になって人工心臓の開発を始めてからも、自分の知らないこと、必要なことはそれぞれの専門家から積極的に学ぶことを心がけた結果、様々な課題を解決することが出来たとのことであった。「壁は自分で作るものだが、それを除くことは出来ますよ」と穏やかに話された言葉は、技術者としての我々に対するまさに頂門の一針であった。(文責 相馬和彦)
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
新たな成長戦略、ライフサイエンス分野への挑戦
- 2007-10-22 (月)
- 異業種・独自企業研究会
と き : 2007年9月13日
訪 問 先 : 富士フイルム(株)先進研究所 訪問
講 師: 執行役員 ライフサイエンス事業部次長 兼 同事業部事業開発室長 戸田雄三氏
コーディネーター: 相馬和彦氏(元帝人(株)取締役 研究部門長)
 平成19年度後半の第二回は、神奈川県足柄上郡開成町にある冨士フイルム先進研究所を訪問した。先進研究所は、冨士フイルムが写真事業から新しい事業分野へ進出する「第二の創業」を担う技術を開発するため、本年2月に竣工を見たばかりの新しい研究所である。そのためか研究所の外装・内装および構造にも、技術開発に掛ける思いや工夫が随所に見られ、会社としての意気込みが感じられた。先進研究所の敷地は周囲を田畑に囲まれていてゆったりとした環境であるが、研究所の外壁には智慧の象徴である青銅製のフクロウが飾られ、建物に入るとすぐにミネルバの銅像が立ち、この研究所が智慧を磨き、新技術を生み出すことを目的としていることを認識させた。
平成19年度後半の第二回は、神奈川県足柄上郡開成町にある冨士フイルム先進研究所を訪問した。先進研究所は、冨士フイルムが写真事業から新しい事業分野へ進出する「第二の創業」を担う技術を開発するため、本年2月に竣工を見たばかりの新しい研究所である。そのためか研究所の外装・内装および構造にも、技術開発に掛ける思いや工夫が随所に見られ、会社としての意気込みが感じられた。先進研究所の敷地は周囲を田畑に囲まれていてゆったりとした環境であるが、研究所の外壁には智慧の象徴である青銅製のフクロウが飾られ、建物に入るとすぐにミネルバの銅像が立ち、この研究所が智慧を磨き、新技術を生み出すことを目的としていることを認識させた。
冨士フイルムは写真フィルム全盛時代に高収益企業として有名であり、その利益基盤を消耗品であるフィルムと印画紙によるビジネスモデルに置いていたことは良く知られている。デジカメの普及に伴って従来のビジネスモデルが時代遅れとなる中で、主要事業から他の新規事業へのシフトが図られて来た。高収益事業である既存事業から新規事業への転換が如何に困難なことであるかは、過去に他企業でも経験されたことであり、失敗例にもことかかない。特に写真事業が高収益事業であっただけに、新規事業へのシフトが一層の困難さを伴ったであろうことは容易に想像出来た。そういう困難さをどうやって克服したかを知ることが出来ることも、今回の訪問で我々が強く抱いた期待の一つである。
 講演ではまず先進研究所の概況について、先端コア技術研究所の五十嵐明副所長から説明があった。先進研究所は組織ではなく、異なる研究所や組織を融合させる場所と位置付けられている。先進研究所の中には、組織としてはアドバンストマーキング研究所、先端コア技術研究所、有機合成化学研究所、ライフサイエンス研究所という四研究所があるが、これも常に固有の場所に分かれているのではなく、マトリックス組織的なもので、むしろ研究テーマ単位で研究員がその場所に集るようになっている。またライフサイエンス研究所(事業部の研究所)以外はコーポレート研究に所属してそれぞれが独立であるが、融合が必要な場合にはフィージビリティーチームを結成して検討し、いけるとなったらプロジェクトチームを作って開発を進めることになる。生産技術の段階に達した場合には、ディビジョナルラボまたは事業部で開発される。因みに技術関連の組織としては、冨士フィルムにはディビジョナルラボ群として、ライフサイエンス研究所以外にはフラットパネルディスプレイ研究所、メディカルシステム開発センター、エレクトロニクスマテリアルズ研究所があり、それ以外にも基盤技術開発センター群として生産技術センター、解析技術センター、ソフトウエア開発センター等多岐に渡る技術開発体制が整っている。
講演ではまず先進研究所の概況について、先端コア技術研究所の五十嵐明副所長から説明があった。先進研究所は組織ではなく、異なる研究所や組織を融合させる場所と位置付けられている。先進研究所の中には、組織としてはアドバンストマーキング研究所、先端コア技術研究所、有機合成化学研究所、ライフサイエンス研究所という四研究所があるが、これも常に固有の場所に分かれているのではなく、マトリックス組織的なもので、むしろ研究テーマ単位で研究員がその場所に集るようになっている。またライフサイエンス研究所(事業部の研究所)以外はコーポレート研究に所属してそれぞれが独立であるが、融合が必要な場合にはフィージビリティーチームを結成して検討し、いけるとなったらプロジェクトチームを作って開発を進めることになる。生産技術の段階に達した場合には、ディビジョナルラボまたは事業部で開発される。因みに技術関連の組織としては、冨士フィルムにはディビジョナルラボ群として、ライフサイエンス研究所以外にはフラットパネルディスプレイ研究所、メディカルシステム開発センター、エレクトロニクスマテリアルズ研究所があり、それ以外にも基盤技術開発センター群として生産技術センター、解析技術センター、ソフトウエア開発センター等多岐に渡る技術開発体制が整っている。
冨士フイルムでは現在を第二の創業に時代と位置づけ、映像文化からQuality of Lifeへ転換しつつある。保有するコア技術の発展・融知・創新により新事業分野へ展開している。その結果、高機能材料、メディカルシステム/ライフサイエンス、情報システム/ソリューション、光学デバイス/コンポーネント事業などへ展開したが、先進研究所ではこれら四事業分野以外の新規分野を探索している。先端コア技術研究所ではフォトニクス、ナノテクノロジー、機能性材料などの5~10年後のコア技術を、有機合成化学研究所では有機エレクトロニクス分野、メディカル/ライフサイエンス分野などで高機能性有機材料による新たな付加価値の創造を、アドバンストマーキング研究所ではインクジェット等新しいマーキング技術の材料・デバイス・システムを開発している。ライフサイエンス研究所では蛋白質および遺伝子の解析/診断システム、創薬/創薬支援、再生医療技術開発、ヘルスケアなどの医療、健康に関するコア技術および商品開発を実施している。
この後研究所の見学を行ったが、全体的にスペースに余裕があり、ガラス張りが多いせいか見通しが大変良好であった。仕事場は少しの例外はあるもののパーティションがないこと、机の配置は迷路のようになっていて移動すると人にぶつかる工夫がされていること、会議室はガラス張りで外から何をやっているかが見えてしまうこと、図書室は個別机が少なく共通机が多いことなど、人と人との接触を可能な限り増加させて融知を起こす様々な工夫がなされていた。
セキュリティーは三段階に区分されたおり、社外の人を入れて交流を深めることと、企業秘密を保持することとのバランスが考慮されていた。研究所の工費は建物本体に150億円、設備投資に今後の投資予定を含めると総額で450億円が投資されている。
冨士フィルムの新規事業の一つであるライフサイエンスの中心として活躍されたおられる戸田雄三執行役員・ライフサイエンス事業部次長兼事業開発部長より、新たな成長戦略としてのライフサイエンス事業のお話を伺った。
メディカルシステム事業では、イメージや印刷でのデジタル化が早く、FCR1903 imagerは1989年に上市した。総合画像診断、形態診断、機能診断、核医学検査などを実施している。核医学検査では、世界でもGEと冨士フイルムの二社による寡占体制を維持している。RI医療では核物質に半減期があるため、定時デリバリーを可能とするデリバリーシステムの確立がコアとなり、他社の参入障壁が高い。内視鏡システムでは、経口に比べて患者の負担が軽いと言われる経鼻のものを上市し、バルーンも保有している。それ以外には、化粧品、創薬スクリーニングシステム、DDS抗がん剤、再生医療なども実施している。
ヘルスケアでは治療よりも予防に注力している。技術としてはナノテク(FTD)、活性酸素の制御、コラーゲン/ゼラチンで培った自社技術などを活用している。化粧品は冨士フィルムとは関連性が低いように見られるが、実は抗酸化物としてのアスタキサンチンをナノレベルで乳化する技術を開発したことが発端となっており、自社技術をベースとしていることは他の新規事業と同等である。再生医療もリコンビナントゼラチンを入手したことがきっかけであり、伝統的に自社技術への拘りが強いことを伺わせた。
新規事業を行ってきた経験から、新規事業を成功するためには三つの要素があると思っている。一つ目は「やりたい」という情熱・夢、二つ目は「やれそう」というリソース(資源)、三つ目は「やるべき」という合理性である。この三つが揃って初めて成功への道を歩むことが出来る。
訪問者には関心が高くかつ示唆に富んだ講演であったので、講演終了後には多くの質問が出た。いくつかを撰んで下記に纏めた。
1.新規事業の選択はトップダウンでなされたのか、あるいはボトムアップなのか?
過去の例は、ほとんどが現業の先にやるべきことはあるか?という研究者の問いかけからスタートしている。そうして生まれた小さな事業を纏めてある規模に達してから、トップはM&Aで事業を拡大することも考えたが、先にM&Aで新規事業を取り込んだことはない。今まではボトムアップが主流であった。
2.新規事業は写真事業に比べ、個々の事業規模は遥かに小粒である。このことは企業文化として問題はなかったのか?
確かに新規事業は個々には小さく、最近では小事業にも慣れて来た。しかし規模としては1000億円規模を目標に探索しようとしている。
3.研究テーマが新規事業を目標とする分だけ成果にはすぐに繋がらす、テーマの継続が難しいのではないか?
会社自体にテーマは自由にやらせる雰囲気があり、将来のためにやっておくべきだという意識が上下で共有されている。従っていわゆるアングラ研究、闇研という意識はなく、明るいところでやれる。ただあまりに自由にやってきたので、これからはステージゲートプロセスの採用などで、テーマの継続/中止などをもっと迅速にやるべきだとは思っている。
質問に関連したコメントとして、冨士フイルムのコア技術は製造技術であり、そのためになんでも自分で作りたがる性癖を有している。例えばフィルムの感光防止技術は極めて高度のレベルに達したので、チェルノブイルで原発事故が起こった際、放射性物質が飛来して製造中のフィルムを感光させることを危惧し、行政から警告が出る前に製造工場を停止したこともあるとのことであった。
また研究開発に関して、これだけの大企業では極めて管理志向が低く、自由な発想を尊重する企業文化を維持しており、その点では大企業でありながらベンチャー企業文化も同じに有する数少ない企業であると思われる。それが過去に写真技術で世界トップの技術を開発し、更にコア技術を発展・融合しながら新規事業へ繋がる技術開発が実施出来る原動力となっていることを実感した一日となった。(文責 相馬和彦)
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
フェラーリチーフデザイナとして活動したものづくり-今日の夢と挑戦
- 2007-10-04 (木)
- イノベーションフォーラム21
と き :2007年9月26日
会 場 :全国町村会館
ご講演 :CEO KEN OKUYAMA DESIGN 奥山清行氏
コーディネーター:LCA大学院大学 副学長 森谷正規氏
 21世紀フォーラム、2007年度後期の第一回は、奥山清行さんの「フェラーリチーフデザイナーとして見た“ものづくり”、そして明日への夢と挑戦」であった。奥山さんは、GMとポルシェでチーフデザイナーを務めた後、イタリアのカロッツェリアであるピニンファリーナに移ってデザイン・ディレクターを務めていて、あの「エンツォ・フェラーリ」をデザインしたことで著名である。いまは帰国して、故郷の山形県で「山形工房」を設けて、木工家具や鋳物のものづくりを指導しており、その製品は海外で評価を高めている。奥村さんはこの8月に「伝統の逆襲-日本の技が世界ブランドになる日」(祥伝社)という著書を出版しているが、日本が進む新たなものづくりに大きな示唆を与える良い本であり、私は毎日新聞で書評に取り上げた。
21世紀フォーラム、2007年度後期の第一回は、奥山清行さんの「フェラーリチーフデザイナーとして見た“ものづくり”、そして明日への夢と挑戦」であった。奥山さんは、GMとポルシェでチーフデザイナーを務めた後、イタリアのカロッツェリアであるピニンファリーナに移ってデザイン・ディレクターを務めていて、あの「エンツォ・フェラーリ」をデザインしたことで著名である。いまは帰国して、故郷の山形県で「山形工房」を設けて、木工家具や鋳物のものづくりを指導しており、その製品は海外で評価を高めている。奥村さんはこの8月に「伝統の逆襲-日本の技が世界ブランドになる日」(祥伝社)という著書を出版しているが、日本が進む新たなものづくりに大きな示唆を与える良い本であり、私は毎日新聞で書評に取り上げた。
奥山さんはまず、イタリアではいかにものづくりをしているのか、それをフェラーリを通して詳しく語った。フェラーリが創業55周年を記念して製造した「エンツォ・フェラーリ」は、7500万円もする超高級車であるが、349台の生産に限定した。フェラーリは車を需要より1台少なくつくることにしており、需要を350台と見込んだのだ。ところが、世界中で大評判になって、申し込みが殺到した。フェラーリは半額の申し込み金を取ったが、それでも申し込みは生産台数をはるかに越えた。そこで、過去の購買実績、所有している車などをもとにしてランクをつくって、上位の者から売ることにしたのである。このような販売がありうるとは、驚きである。
なぜ、フェラーリはこのように非常に高い人気があるのか。それは、顧客がフェラーリの過去を買っているからだという。フェラーリの顧客には事業に成功した大金持ちが多いのだが、いまではふんだんにお金があって、何でも買うことができる。ただ買えないのが過去であるが、フェラーリは過去においてF1を中心にしたさまざまな伝統があって非常に大きい蓄積があっていまに至っているのであり、そのフェラーリを買うことは、過去を買うことになるのだという。高度な工業製品は未来の匂いがするものなのだが、こうした特別な製品は、過去を背負っているのである。過去を買うと言うのはとてもユニークな視点であり、今後の高級製品のありかたに示唆を与える。
 ピニンファリーナがフェラーリから「エンツォ・フェラーリ」を受注する経緯も詳しく語った。それはとてもドラマティックなものであった。いろいろとデザインしたがフェラーリの社長の承認がどうにも得られず、いよいよ最後となってもOKが出ず、社長は帰ろうとして乗ってきたヘリコプターのエンジンをスタートさせた。だが、サンドイッチでもどうぞと引き留めて、奥村さんはその間の15分の間に新たなデザインを描いて、社長に見せて、ついに承認を得ることができた。発注者とデザイナーの間で、両者のきわめて鋭い感覚が一瞬の接点を生んだのだろう。
ピニンファリーナがフェラーリから「エンツォ・フェラーリ」を受注する経緯も詳しく語った。それはとてもドラマティックなものであった。いろいろとデザインしたがフェラーリの社長の承認がどうにも得られず、いよいよ最後となってもOKが出ず、社長は帰ろうとして乗ってきたヘリコプターのエンジンをスタートさせた。だが、サンドイッチでもどうぞと引き留めて、奥村さんはその間の15分の間に新たなデザインを描いて、社長に見せて、ついに承認を得ることができた。発注者とデザイナーの間で、両者のきわめて鋭い感覚が一瞬の接点を生んだのだろう。
これは、発注者とデザイナーの間の重要なコミュニケーションであるが、奥村さんはデザイナーは関連する多くの人たちとの間でのコミュニケーションを密にしなければならないと言う。開発部門、生産部門、販売部門、顧客などとの間での広く深いコミュニケーションがあってこそ、良い製品が生まれるのである。さらにデザイナーにとって仕事でまず必要であるのは、コンセプトづくりであると言う。この点は著書でも力説している。一般には、デザイナーは外見をかっこ良くする仕事と思われがちであるが、製品のコンセプトづくりからスタートするのであり、それが製品を大きく左右する。デザイナーは、コンセプト、デザイン、コミュニケーションにそれぞれ3分の1の力を配分するのだと言う。
 イタリアに優れたブランドが多いのはなぜか、その由縁も語ったが、ブランドは顧客が育てるものだと言う。イタリアでは、庶民は所得は多くはなく、生活はとても地味だが、少ないお金を有効に使おうと懸命に努力する。そこで、物をただ買うのではなく、製品として厳しい目で見て、口を出していろいろと注文をつけるのである。それに応えることで製品は洗練されて、ブランドとして育っていく。一方日本では、大企業の製品であればみなが信用して、何も言わずに買ってしまう。それはよろしくないのである。
イタリアに優れたブランドが多いのはなぜか、その由縁も語ったが、ブランドは顧客が育てるものだと言う。イタリアでは、庶民は所得は多くはなく、生活はとても地味だが、少ないお金を有効に使おうと懸命に努力する。そこで、物をただ買うのではなく、製品として厳しい目で見て、口を出していろいろと注文をつけるのである。それに応えることで製品は洗練されて、ブランドとして育っていく。一方日本では、大企業の製品であればみなが信用して、何も言わずに買ってしまう。それはよろしくないのである。
これからのものづくりについては、農耕型であるべきと説いた。これまでのように技術をネタにして何かを探そうと努力しても、今の時代では良いものは見つからない。そこで、これから何が求められるのかを探って、タネを植えるというのである。あるいは、デザイナーはシェフであるべきだとも言う。供する料理のメニューを自らつくるのである。それがコンセプトをつくることにもなる。
アメリカ、イタリアで素晴らしい業績を上げた奥村さんの話しは、やはり凄みがあって、みなが聞き入った。新しいものづくりを大いに考えさせられる一時であった。
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
Home > アーカイブ > 2007-10